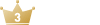日本文化と榊
日本文化と“榊”(ウィキペディア フリ-百科事典より)
日本では古くから神事に用いられる植物であり、「榊」という国字もそこから生まれた。
古来から、植物には神が宿り、特に先端がとがった枝先は神が降りるヨリシロとして若松やオガタマノキなど様々な常緑植物が用いられたが、近年は、もっとも身近な植物で枝先が尖っていて神のヨリシロに相応しいサカキやヒサカキが定着している。
家庭の神棚にも捧げられ、月に2度、1日と15日(江戸時代までは旧暦の1日と15日)に取り替える習わしになっている。
神棚では榊立てを用いる。
田舎などでは庭先に植えている家庭が多い。また、常緑樹でもあることから庭木としても使われていることがある。
名称 [編集]サカキの語源は、神と人との境であることから「境木(さかき)」の意であるとされる。常緑樹であり繁えることから「繁木(さかき)」とする説もあるが、多くの学者は後世の附会であるとして否定している[要出典]。
混同されやすいので、榊は「本榊(ホンサカキ)」とも呼ばれ、ヒサカキについては、「シャシャキ」「シャカキ」「下草」「ビシャコ」「仏さん柴(しば)」「栄柴(サカシバ)」などと地方名で呼ばれることもある。